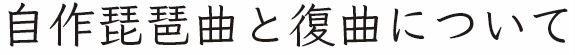◼️2025年 復曲「水の新潟」(五十嵐雅水作 髙橋育世編)について

琵琶曲「水の新潟」は、今から40年ほど前に、新潟市出身の琵琶奏者、故五十嵐雅水によって作られました。
その中には、豊かな水の恵みと共に暮らす、その時代の新潟の町の姿が描かれています。
当時、五十嵐雅水師に師事していた私は、できたばかりの新曲として、この「水の新潟」を伝授頂きました。
2022年に新潟琵琶楽協会に復帰した際に、今はもうこの曲を弾く人はいない、という話をお聞きして、是非この曲を蘇らせたいと思いました。
「水の新潟」に描かれている新潟の姿は、写実的であるのが特徴です。
例えば、新潟のイメージとしてよく語られる「お堀と柳」という情景は、この曲には登場しません。
今、実際に見ることができる町の姿だけをそのままに写しているのは、師匠五十嵐雅水のこだわりだと思うのです。
その精神を受け継いで、この度の演奏では、「令和の今の新潟の姿」として違和感のないよう、師の詞章を極力変えないようにしつつ、細部を改訂いたしました。
共演の瞽女唄奏者金子まゆさんによる、民謡「佐渡おけさ」を曲中に挿入したのも、新しい工夫です。
このように曲に変更を加えることの是非は、慎重に考えなくてはならないと思いますが、私の習った流派の琵琶曲においては、演奏者の工夫によっての細部の変更が比較的許容され、実際に行われて来ているということがわかり、また、師匠五十嵐雅水が、自作曲を他の奏者に提供する際にも「変更自在」(変えて良い)と、書き添えられていた、という証言もお聞きしましたので、思い切って、新たな工夫をしてみることと致しました。
2022年10月、新潟市は、ラムサール条約の湿地自治体認証制度に基づく「国際湿地都市」に、日本で初めて認定されました。
この令和版「水の新潟」で、先人の郷土への熱い思いに触れるとともに、私たちの「新潟」の豊かな水の風景に、あらためて思いを馳せていただければ幸いです。


◾️2024年新作「板額御前」について

2024年11月10日 新潟市の新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ、能楽堂。新潟琵琶楽協会の「琵琶楽演奏会」にて、初演いたしました。板額会による舞と共演の舞台でした。
◾️板額御前
板額御前(はんがくごぜん)は、鎌倉時代の新潟(現在の胎内市)に実在した女性武将です。
私が板額御前という名前を知ったのは、もう30年以上も前のことです。
琵琶の師匠、故五十嵐雅水先生と、板額御前の曲を作りたいというお話で楽しく盛り上がった思い出があります。
師匠が先に仰ったのか、私がどこかで板額のことを知って、師匠
にご相談したのか、その辺ははっきり覚えていないのですが、当時、新しい曲をどんどん作るようにと勧められ、おりましたので、この板額御前も、その中の一つだったと思います。
結局、その当時は調べても情報が少なく、曲を作ることができませんでした。
しかし、板額御前という名前は、忘れることなくずっと頭の片隅にありました。
五十嵐先生の遺稿の中にも板額御前の曲は無かったそうなので、師匠もまた、
この曲を作り上げてはいなかったようです。
私はその後長く琵琶を中断していましたが、琵琶を再開した2022年に、
これも長年の宿題だった戊辰戦争の長岡の戦いでの長岡城奪還の物語「八丁沖」を作りました。
そして、次の宿題として自然に思い浮かんだのが、この板額御前の物語でした。
「八丁沖」の時にもそうだったように、30年前の、「調べても調べてもわからない」
という状態が嘘のように、現在では「板額御前」をネットで調べただけで、たくさんの情報がありました。
その上、2022年に制作に参加させていただき、私が琵琶を再開するきっかけにもなった「大里峠大蛇伝説」の舞台の関川村が、板額御前の住んでいた胎内市のすぐお隣、という奇遇で、大蛇伝説でお世話になった関川村の方に、板額御前をご存知ですか?とお聞きしたら、あっという間に、お知り合いの、胎内市の「板額会」会員の方をご紹介くださり、これもまたあっという間に、板額会より、沢山の資料をお送りいただく、という、願ってもないような幸運がありました。
大蛇伝説は、制作中に本当に不思議なことが次々に起ったのですが、こんなところまで繋げてくれるとは、驚くばかりです。
「板額御前」は、静御前、巴御前とともに、三大御前、と呼ばれる女性です。
一般的には静御前、巴御前の方が有名で、大河ドラマにもこの二人は度々登場していますが、実は、この三人の中で実在したことがはっきりしているのは板額御前だけだそうです。
板額御前だけが、鎌倉幕府の公式歴史書「吾妻鏡」に登場するのです。
そこには、鎌倉幕府の軍勢の敵(板額の一族である城(じょう)氏は平家方)として、得意の弓を使い戦場で一族の男性に勝るとも劣らない奮戦をする板額御前の勇姿が、驚きを持って記されています。
曲を作るにあたり、まずこの吾妻鏡に記載されている板額御前の姿をそのまま取り入れる、ということは、当初から考えていたことです。しかし、吾妻鏡の記載は量も多くなく、しかも敵である鎌倉方の視点から一方的に見た姿です。琵琶の曲とするには、これだけでは足りないものがある、と感じていました。
ちなみに、静御前、巴御前の曲は琵琶曲として昔から存在します。
史実では実在が怪しいこの二人ですが、琵琶の世界では人気の曲目です。琵琶曲の静御前は、悲運の女性静の、義経に対する思慕の情と白拍子としての矜持。巴御前は女武者としての圧倒的な強さに加えて、木曽義仲への忠誠心と愛情がテーマかと思います。
では、この2曲に並べて板額御前の曲を作るとしたら、吾妻鏡の板額御前の姿に、更に加えるものは何でしょうか?
それは、板額の心情ではないでしょうか。
それを補うために、曲を作り始めるにあたって、板額会の方からお話を伺うことができたのは大きな助けになりました。板額会の皆さんが長年調査研究された結果、諸説ある中、おそらくこうであろう、と推測されている板額の姿や、地元に伝わる伝承、板額御前への思い、などをしっかりとお聞きすることができました。
足りないと思っていたものを組み立てるためのパーツが、お聞きしたことの中にたくさん見つかって、板額という人の、単に「驚くほど強い女武者」というだけではない姿が思い浮かぶようになりました。
曲作りに取り掛かり、ほぼ形が出来上がりかけた頃、ちょうど、板額御前の物語の「鳥坂(とっさか)城の戦い」があった季節になりました。
情報が得やすくなった今でも、その場所に立ってみて初めてわかることがある、というのは、前回の「八丁沖」の制作の時に大いに実感したことだったので、今回も、その季節に、現地に行ってみたいと思っていました。
板額御前の守る鳥坂城が陥落したのが建仁元年の旧暦5月のはじめ、西暦に直すと1201年の6月の初旬ということになります。
私がここを訪問したのはゴールデンウイーク中だったので、ひと月ほどの違いはありますが、春が終わり本格的な夏が始まる間の、一年の中でも比較的穏やかな季節が、戦いの行われた時期だったという感じは実感できました。

鬱蒼とした山道、大きな木々です。山の匂いがします。

山道横に設置された看板、予想をはるかに超える広さで、鳥坂城と板額御前の一族、城(じょう)氏の領地「奥山荘」が地図上に示されています。
山城という言葉から、小さめのお城一つを一点で思い描いていた私の予想は打ち砕かれました。
それとともに、曲の中に入れさせていただくことになっている、遠藤都美桜先生作の詩吟の中の一節「奥山の荘眺は彩雲連なり」の言葉に、山々を超える壮大な広がりのイメージが浮かびました。
やはり来てみないとわからないことがあります。

鳥坂城のあったと思われる山のいただき、遠望。ひっきりなしに鳥の声がします。こんなのどかな季節に戦が行われたのです。今は静かに見えるこの山の上に、かつてたくさんの人々が活動して、栄枯盛衰のドラマがあったと思うと、不思議な感慨を覚えます。


いたるところに山の花が咲いていました。板額御前もこんな花を見て暮らしていたのでしょう。
こうして、新作の琵琶曲「板額御前」に、現地で感じたことも加えて、
私なりに納得のいく形を整えることができたと思っています。

◾️2022年新作「八丁沖」長岡城奪還 について

第70回新潟市芸能まつり 琵琶楽演奏会 2022年11月6日りゅーとぴあ能楽堂
◾️八丁沖の戦いとは
慶応四年(1868年)旧暦7月24日(新暦9月10日)。戊辰北越戦争。
西軍の攻撃により落城、占領されていた長岡城を奪還するべく、家老河井継之助の指揮の下、長岡軍600〜700名が、城下の北東側に広がっていた大沼「八丁沖」(大きさ南北5キロ東西3キロ)を深夜に密かに渡り、奇襲攻撃によって長岡城奪還に成功した、という戦いです。
2022年に、約30年ぶりに
琵琶の演奏会に復帰することとなり、
復帰にあたり、30年前に故五十嵐雅水師のもとで構想を始めたものの、当時資料が乏しく完成に至らなかった、郷里長岡の戊辰北越戦争の物語「八丁沖の戦い」を題材にした、「八丁沖 長岡城奪還」を完成させて出演することといたしました。
30年前は、この「八丁沖の戦い」を調べて曲を作るには、図書館で資料を探す、詳しい人を探し当ててお聞きする、など、方法も限られていました
。しかし、30年の間に、インターネットで情報を探すことができるようになったり、新たに河井継之助や戊辰戦争の記録の施設が造られたりして、調べる方法が飛躍的に増えていたのは嬉しい驚きでした。
かつて、調べても調べてもわからなかったことが、瞬く間にわかりました。一方で、それを「琵琶の曲」として聞いていただくには、何をどんなふうにお伝えしたら琵琶らしい姿なのか?
という疑問も出て来ました。 ネットの上の情報は戦争の様子を詳しく伝えてくれますが、その情報を並べただけでは、大切なものが足りない、という感じが徐々に強くなりました。
◾️現場 八丁沖

曲が八割ほど形になってきた頃、現地「八丁沖」に行くことができました。
これは、とても貴重な経験でした。
長岡の中心市街の東北、見附市との境界付近まで広がる八丁沖の跡地は、今は干拓されて水田になっていますが、大沼の痕跡は今でもありありと地形に感じられ、その広さは想像以上でした。
向こう岸から上陸地点までも遠いですし、上陸してから長岡城までも予想以上に距離があって、ここを渡って城に向かって攻め進み奪還に成功した長岡の武士の覚悟と苦労が、想像を絶するものだったことが窺えます。
吹き抜ける風の感じ、そこから見る山の形、虫の音、今でも付近を豊富に流れる水の音、ここに来なければわからなかったことが多くあって、来て良かったなと思いました。

写真の広々とした水田一帯が、かつての大沼「八丁沖」の現在の姿です。
わたしが立っているところが、背後の向こう岸から、夜間六時間もの時間をかけて泥沼の中を渡ってきた長岡軍が未明に上陸した地点で、今は「八丁沖古戦場パーク」という小さな公園になっています。